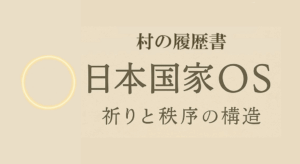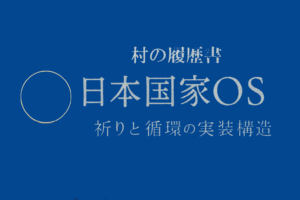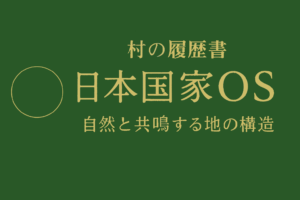信濃国【安曇野】大海の龍—八百万の水神となりて龍口を拓く

海を発ちて、山に祈る ― 水の龍、信濃へ遡る
かつて呉越の乱を逃れた一族は、海を渡り倭へと至り、やがて白村江の敗戦を経て信濃の地へ封じられました。
しかし彼(か)の氏は滅びず、水を治める技をもって荒地を潤し、穂高見命を祀りて新たなる龍の口を拓いたのです。
海の記憶を胸に、山にて水を祀る民――。その祈りはやがて諏訪へと伝わり、今も清き水脈のごとく安曇野の大地に息づいています。
第一章|龍翔ける大地 — 海原の覇者
遥かなるいにしえの時――
龍昇る大地、長江の広き河口で、呉と越なる海の民が、たがいの覇を競い合っていました。
越は呉を滅ぼし、さらにその越もまた、中原の勢力によって亡びの道を辿ってしまったのです。
そんな折、乱れし世を逃れ、大海へと漕ぎ出した海(あま)の一族がいました。
かの徒(ともがら)は、まるで海の龍に乗るかの如く、潮の流れに身をまかせ、倭の国の南なる小さな島へと辿り着いたのです。
――その名は、安曇野(あづみの)と申します。
鯨のごとく巧みに船を操り、龍のごとく水を治める術に秀でた者たちでした。
その比類なき海(あま)の才は、やがて倭国にても広く知られて、やをらにその龍威を世に知らしめていったのです。
かくして、ついに国の海の要衝を任せられるほどの、深き信を得るに至りました。
高き連(むらじ)の位を給はり、政に仕え、海の龍なる民として、その名をいにしえの世に広く馳せたのです。
かの力、まさしく海の龍のごとし—。
荒ぶる波を裂きて進むその船は、鯨面も逞しき威風であったと申します。
呉越より海を渡りし一族は、倭国の海を護りし龍として君臨したのです。

第二章|白村江の暮潮 — 山に鎮まる龍魂
かくして時は下り――
安曇野なる連は、朝鮮半島・白村江の戦にて、倭軍の主たる役を命じられました。
されど抗ふすべもなく、唐・新羅の大軍に屈し、大いなる敗戦を蒙(こうむ)ったのです。主なる者は海に沈み、生き残りし者たちは、ヤマトの都より遥か遠き、信濃の僻地に封じられました。
かの地は、八百万の神さえも棲まぬと伝えられる、実り乏しき東(あずま)の荒蕪(こうぶ)だったのです。
されども、安曇野なる一族は、ただの海人にあらず。
水を治める神の技をもつ者どもにして、泉小太郎と呼ばれし者の導きにより、
山を崩し、水を引き、大地をひらいて、新たなる龍命の地を築いたのです。

第三章|山に棲まう水龍 — 蘇りし古(いにしえ)の魂を紡ぐ
かくして、大陸より蘇りし海の民は、己が祖なる船を神にかたどりて、社を築き、祈りを奉じました。祖神・穂高見命をまつり、遥かなる海の記憶と、遠つ御霊を、八百万の水神に託したのです。
この地を、あらたなる故郷と定め、龍なる水魂(みたま)を鎮めました。
われら、この山の要の地にて、水の龍とならん。この荒ぶる大地を潤し、命の龍口を拓かんとす。
その海神(わたつみ)の魂言(たまごと)は、大いなるうねりとなり、諏訪の大神、縄文より続く信濃の八百万の神々にも届いたのです。
大祝(おおほうり)の神は、静かに、されど深く頷きました。
かくして、ときは流れ、世は移りていったのです。されどいまも、安曇野なる海の民は、水脈のごとく大地に息づいています。
龍の口より湧き出づる清水は、この地を静かに、されど確かに潤し続けているのです。

📜安曇野之巻、了
地図を開く ▶
海と山、天津と国津を接続する循環型統合OSの要(かなめ)は、いまも龍口の清水に国家秩序の呼吸を呼び覚ましている。
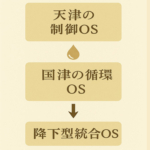












-150x150.jpg)