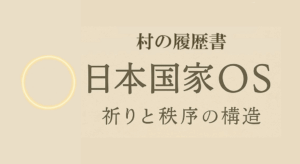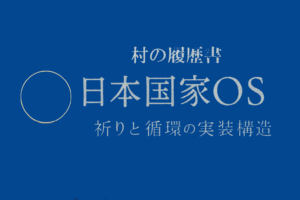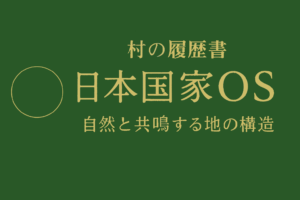信濃國【南木曽町】— 谷を越え、時を紡ぐ縁(えにし)の地

南木曽町|谷を越え、義を紡ぐ道の誇り
古来より旅人や軍勢が峠を越えて東西を結び、そのたびに里人は黙して道を守り、安堵の架け橋となってきたのです。
木曽義仲もまた、この峠を越え、京をめざしたと申します。
里人は焚火を囲み、祈りを託し、義仲の軍は谷を越え、武士の世の明けを告げました。
その足音は時を超えてなお山あいに息づき、南木曽は“義と祈りを架ける護り橋”として今も在り続けているのです。
第一章|義仲を迎えし峠道にて—焚火の刻、静かに燃ゆる誓い
南木曽町――
その急峻なる峠は、古代の東山道、吉蘇路、そして中山道といった大路が交わる、まさに「縁(えにし)の地」でした。
山深き道を、時に命を懸けて渡る者たちを、この地の民は、黙して見守り、陰ながら支えてきたのです。
かつて、ここ南木曽の山間には、谷を越え、峠を踏みしめながら、東西を結ぶ旅人たちの足音が響いていました。
木曽義仲もまた、この地を京へ上る宿(しゅく)として選んだのです。
村の者は、時として、要人の命託されしこの危うき峠道を、声もなく、ただ黙々と、されど確かに――守り継いできました。
それは、己らの誇りにして、生きがいでもあったのです。
その夜、谷の底にて、焚火を囲む村の者たちの姿がありました。
「いつ義仲さまがお着きになってもよいよう、用意を怠るでないぞ。」
その一言が、夜の影に、静かに沁みわたってゆきました。そして、者どもは、祈るがごとく、黙して頷いたのです。
-300x139.png)
第二章|勝鬨の声、谷を越え、義の橋を架けんとす
急峻なる谷間に陣を張る義仲の姿は、
まさに天より龍の舞い降りたるがごとく——。
その勇姿は、新たな世の幕開けを告げるかのようであったと申します。
それを静かに、されど誇らしげに見守る者どものあいだに、
ひとときの安堵が、そっと広がっていったのです。
やがて時は、幾世の代を重ねてゆきました——
されどその誇り高き想いは、絶えることなく脈々と受け継がれていきました。
そして今もなお、奢れる平家を討たんとする“縁の地”として、己が誇りを、静かに、あすの刻(とき)へと架け続けているのです。
天の津より授かりし、この地の祈りは——
東(あずま)と西(にし)とを結ぶ、“心の架け渡し”なり
-300x139.jpg)
地図を開く ▶
南木曽は、龍蛇の荒ぶる地脈をはらむ峠にて、天津神の理を橋として通し、国を貫いてきた。中央が乱れれば、国津の基盤を呼び起こして秩序を立て直す——“国家OSの調停核”として息づいている。
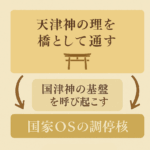













-150x150.jpg)