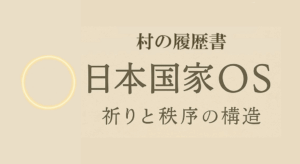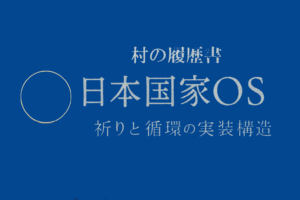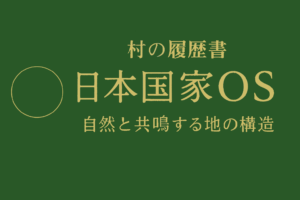日本国家OS|卑弥呼と箸墓 ― 旧OSから新OSへの転換点
第一章|旧OS:日本海ネットワーク(縄文的基層)
卑弥呼の邪馬台国は、『魏志倭人伝』に描かれるように、入れ墨や海民的風俗を持つ共同体でした。
これは日本海沿岸から北九州にかけて残っていた縄文的な海洋ネットワークを基盤としていました。
さらに重要なのは、卑弥呼が祈りと占いを通じて国々をまとめたシャーマン的存在だった点です。
これは後の出雲「国譲り」における、幽(かく)りごと=祈り・霊的基盤 と 顕(あらわ)ごと=秩序・富の管理 の役割分担を先取りしており、日本国家OSの原型を示しているのです。
第二章|新OS:奈良盆地ヤマト王権(稲作中央集権)
240〜270年頃に築かれた箸墓古墳は、巨大前方後円墳の最初期でした。
それはまた、稲作富を集約・管理する中央集権の象徴であり、
馬や騎馬戦の導入とともに「稲作+軍事+中央集権」という新OSが(新しい基盤)整えられていったのです。
第三章|「国譲り」の神話的構造
-
旧OS=大国主(海・縄文的基層・祈りの力)
-
新OS=建御雷・天津神(稲作・中央集権・顕ごと)
この「国譲り」神話の構造は、卑弥呼から箸墓へ、旧OSから新OSへ移る歴史的転換を象徴しているといえます。
第四章|軸の整理
-
旧OS:縄文ネットワーク型(海・交易・祈り)
-
新OS:弥生中央集権型(陸・稲作・軍事)
-
卑弥呼と箸墓:その交差点に現れた「二重構造の転換点」
卑弥呼は、縄文的な祈りの力で国々を結んだシャーマン的女王でした。その後に台頭したヤマトは、稲作と軍事を担う「中央集権の秩序」へと移行していきます。
卑弥呼は、まさにこの二重構造がせめぎ合う転換期を体現した存在だったのです。
📘 このテーマをさらに掘り下げた考察記事はこちら(note) ▼
日本国家基盤の二重構造を映す卑弥呼の存在


















-150x150.jpg)