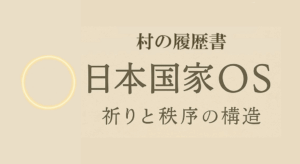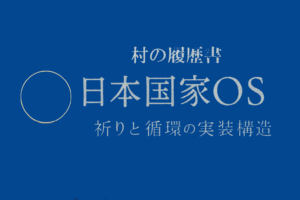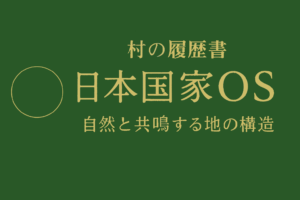泰阜村OS — 八百万の基盤に立つ共生の理
泰阜村の歩みは、単なる「辺境の暮らし」ではありませんでした。戦乱を逃れた人々がこの地に集い、出自の違いを越えて手を取り合い、自然と共に生きる道を築いたのです。
それは、縄文以来の共生的基盤の上に、武士や落人といった異なる出自を溶け込ませてきた“再土着型の共生OS”でもありました。
1. 縄文の基盤――天竜川と共生の里
南部・天竜川沿いの肥沃な地では、縄文以来の共同体文化が息づいていました。人々は自然の恵みを享受し、狩猟・漁撈・農耕を重ねながら、和をもって生きる文化を築いてきたのです。
2. 戦乱と流入――敗者を受け入れる村
鎌倉・南北朝の戦乱で敗れた人々は、泰阜にたどり着きました。三浦一族、林一族などが谷に庵を結び、南山衆が結束しました。
ここでは出自や立場を越えて、人々が「仲間」として迎え入れられたのです。
3. 知久氏と国津の信仰
鎌倉期、この地を治めた知久氏は諏訪神党の系譜に連なっていました。
しかし泰阜においては「戦う神」よりも「自然を敬う神」が重んじられ、土地と共生する信仰が強く受け継がれました。
その結果、村は中央の戦乱に巻き込まれにくく、穏やかな暮らしを保つことができました。
4. 南北の二重性――共生と開拓の統合
南部では「自然との共生文化」、北部や山間部では「開拓と協力の文化」。
異なる基盤を持つ二つの世界が、互いを補い合いながら結びついたことで、泰阜村は独自の共同体OSを形成しました。
5. 基盤OSとしての永続――共に育む心
泰阜村の「共生OS」は、いまも土地に根差して動き続けています。
フラットな人間関係、互いを受け入れる心、自然とともに生きる知恵――それらは現代においても、日本の魂を支える基盤であり続けているのです。
泰阜村は、八百万の神々に根ざした国津の基盤。
南山の結束、稲伏戸の祈り、我科の庵――それぞれの系譜が交わり、出自を越えた共生共同体を形づくった。
その“基盤OS”は、大地に根差して生きようとするものを受け入れ、日本の魂を支える柔らかな基(もとい)となった。





















-150x150.jpg)